今回は冬の代表的な果物「みかん」について書かせてもらいます。自分が子供の頃には冬になるとダンボールにいっぱい入ったみかんを買ってきてはコタツでおやつ代わりに食べていました。時には1日5,6個ぐらい食べるときもあって手のひらが黄色くなることも。ミカンは日本人にとても馴染み深い果物ではないでしょうか。

みかんの歴史
みかんの発祥は諸説ありますが、インド、ミャンマー、タイあたりでそこから中国に伝わり広く栽培されたと言われています。日本の文献で最初にみかんが登場するのが「古事記」「日本書紀」であり平安時代頃にはすでにあったと考えられます。当時のみかんとしては食用というよりもむしろ薬用として使われていたようですね。
日本で今現在食べられている温州みかんとしては、もともと中国から小みかんとして九州に伝わり、それが江戸時代前期頃に和歌山県(紀州有田)に移植されて一大産業として栽培されました。そこから温州みかんとして最も有名な紀州みかんの名前がついたのです。
温州みかんは当初種子を生じないこともあって武士の世界では縁起が悪い物とされてあまり栽培されることはなかったのですが、江戸時代後期あたりからその美味しさが知れ渡り、広く栽培が行われるようになっていきました。
明治時代になるとさらに栽培が盛んになり、和歌山県以外でも静岡、愛媛でも栽培され量産されるようになりました。1960年代の高度経済成長の流れを受けて日本人には欠かせない果物になっていきました。
みかんの栄養素
みかんに含まれる栄養素としては、ビタミンCや食物繊維が豊富に含まれている事で知られています。
ビタミンCは抗酸化作用があり、免疫を高めたり、お肌の調子を整える作用が期待されます。
ビタミンCは熱に弱く、加熱すると組織が壊れて吸収されにくくなるので、そのまま食べれるみかん等の果物からは効率よくビタミンCを吸収することが出来ます。
食物繊維はミカンの薄皮や房についている白い筋に多く含まれています。整腸作用があり便秘の解消や食後の血糖上昇を緩やかにする作用があります。また白い筋にはヘスペリジンという成分が含まれていて、コレステロールや血圧を低下させる作用が報告されています。
その他注目される栄養素としてβクリプトキサンチンという成分があります。βクリプトキサンチンはビタミンAに変換される前駆物質で代謝されてビタミンAになります。骨代謝の働きを助けることにより骨の健康維持に役立つと言われています。
薬用としてのみかん
みかんは古くから薬用としても大変重宝されています。薬用としては果実の部分よりも皮の部分を乾燥させた陳皮が漢方薬に使用されます。
陳皮は理気剤に分類され、胃腸の動きをよくしたり、鎮咳去痰作用があり六君子湯、平胃散、補中益気湯など多くの方剤に含まれています。
また皮を良く洗い、天日干ししたものをネットなどに入れてお風呂に入れると入浴剤としても使えます。特有に香りでリラックスできますし、血行促進作用で冷え症にも効果的です。
今回はみかんの効能について書かせてもらいました。みかんを沢山たべて寒い冬を乗り切りましょう。
参考:Wikipedia

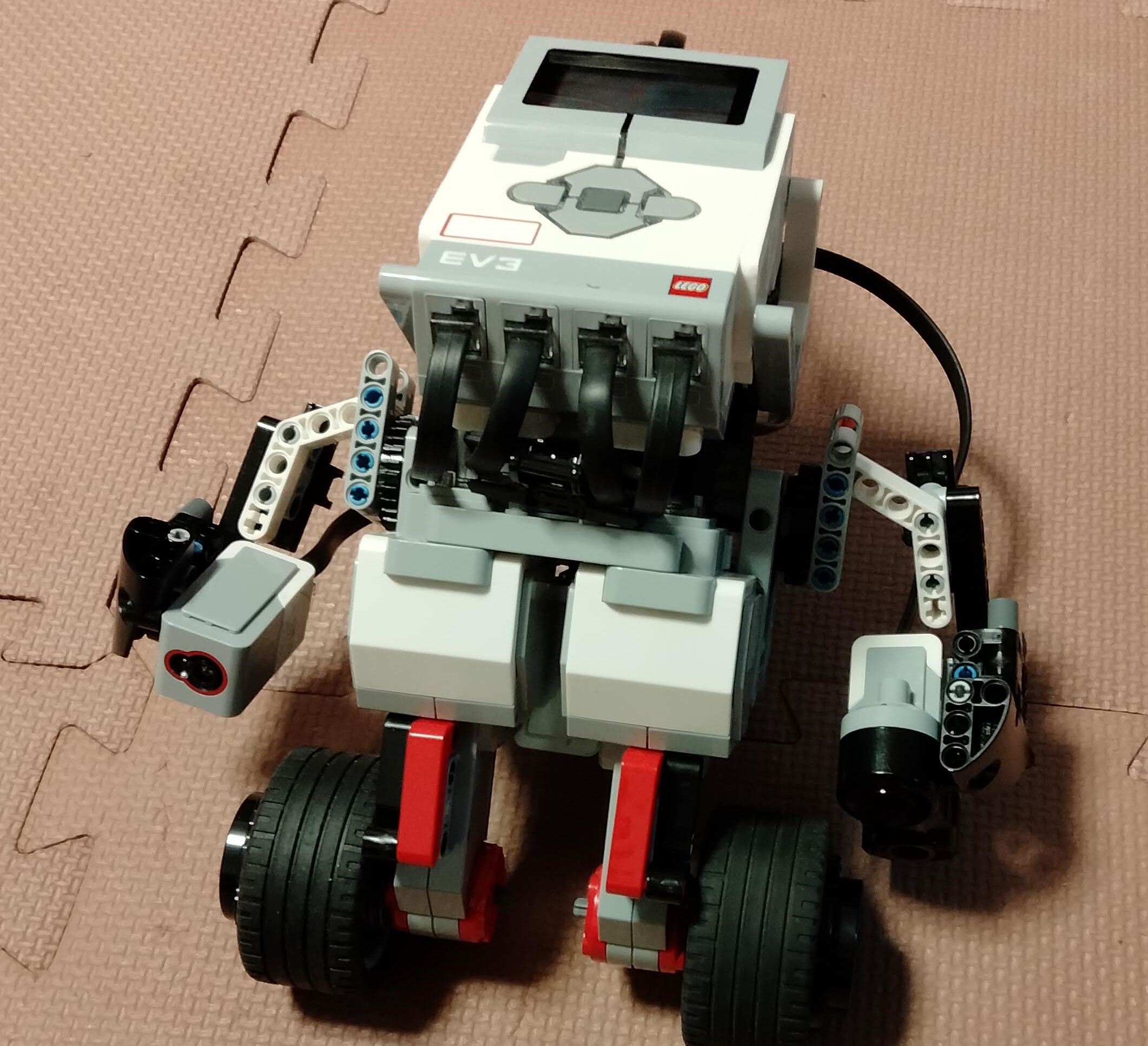

コメント